もうひとつのインビジブル・ハンド #1/遥兵
電話を終えてひとまず自室に戻ったら、ダンボール箱五つ分の全財産はすでに廊下に積みあげられていた。
先輩たちが手分けして二階へ運んでくれたのだろう。玄関先に置いたままではあとがつかえてしまう。なにしろ今日は新入生の私物がひっきりなしに届く日なのだ。朝から中等部の寮とこの霧船寮をトラックが何往復もしている。
軍手をはめて機敏に動き回る先輩たちを、遙兵は心底すごいと思った。共同生活は人を働き者にするのかもしれない。
中等部の寮では住み込みの管理人さんが力仕事を引き受けてくれたが、高等部ではそうはいかない。これからはなんでも自分たちだけでできるようにならないと。
なにはともあれ、この忙しいときに、祖母の長電話には閉口した。年寄りというのはどうして同じ話を何度もしたがるのだろう。そろそろ終いだろう、もう切らせてもらえるだろうと思わせておいてまた話を蒸し返すのだからたまったものではない。
いま忙しいからと邪険に切ってもよかったのだけれど、小さい頃からのおばあちゃんっ子だった遙兵はけっきょく最後までつきあってしまった。どうせ電話代はかけてきた向こう持ちだし、こんなときでないと祖母には話し相手すらいない。孫との会話が残り少ない人生の活力というのなら、それでいいじゃないか。
帰省したら帰省したで上げ膳据え膳でもてなしてくれる。卒業祝いと入学祝いを別々にくれただけでなく、新幹線のホームでこっそり手渡してくれた封筒には餞別と称して折り目のない十万円が包まれていた。
大事にされているんだなあ、といまさらながらに思う。
有名な超進学校でがんばっている自慢の孫。女系家族の猛地家にようやく授かった男の子。かわいくないはずがない。
ほんとうならば地元の高校にかよわせて、好きなサッカーを思う存分させてあげたかったのだと、別れ際に祖母はつぶやいた。
まかりまちがえば望まずともそのようになっていたかもしれないぜ、ばあちゃん。
喉元まで出かかったその言葉を遙兵は飲みこんだ。高等部に進学できたのはまぐれであるなどと、笑って謙遜したところでよけいな心配ごとを増やすだけであろう。
中等部に引っかかっただけでも一族郎党がざわめいたのに、さらに難関と噂される高等部に進学が決まったときは、親戚の人数がいきなり十倍に増えたような騒ぎになった。顔も名前もろくに知らない親戚のそのまた親戚からもったいないくらいのお祝いをつぎからつぎにいただいて、寝る時間をけずってお礼の手紙を書いたくらいである。母が礼儀に関しては口うるさい昔気質の人なので、こういうことはきちんとしておかなければあとでどんな小言をくらうかわからない。ある意味それは、ダメモトで受けた選抜試験よりもはるかに精神的拷問に近かった。
猛地家は明治時代からつづく老舗のきりたんぽ屋である。先祖代々、秋田名物きりたんぽを焼いて売ってきた。商売人の家系だからさぞかし由緒正しく、土地に根付いた伝統を守り、かつ秋田県のために経済貢献をしているかといえばあいにくそういった事実はない。
たとえば店のあるじは食品衛生法のなんたるかも理解しようとしない当世きってのつむじ曲がりだ。
五代目を襲名した父は典型的な職人タイプのいわゆる理想論者で、美味美麗なきりたんぽ以外にはまったく興味のない男である。視野の狭さも天下一品、こときりたんぽがからむと周囲がまったく見えなくなる。経営なんぞは従業員にまかせておけばよいという、とても危なっかしい理屈で現実に儲けているのだからお見それするしかない。
ただひとつの例外が母だ。大恋愛の末の結婚だったらしいが、そのあたりの情報には当事者による捏造の匂いがぷんぷんするので、あえて触れずにおく。
きりたんぽと、きりたんぽのような白い肌の秋田美人妻を溺愛することにつけては天下一品の父。それ以外のところをフォローするためにひとり息子はまだ幼いうちから過度の期待を背負わされてきた。
この期に及んで家を継がないなどと爆弾発言をしようものなら、一族は慌てふためくにちがいない。しかたないねと笑ってくれるのはおそらく、後先顧みない父と母と祖母くらいなものだ。
べつに六代目を継ぐのが厭なわけではない。それ以外にしたいことがあるというのでもないし、家のきりたんぽは日本一だとも思っている。
ただ、敷かれたレールに乗るだけというのも癪なのである。
自分はべつに、他人を喜ばせるために将来を決めるつもりはないのだから。それこそ顔も名前も知らない疎遠な親戚にいくらとがめられようと、知ったことではない。自分の将来は自分のものだ。
中学校の三年間、ついでに高校の三年間、実家を離れることにしたのは正解だったかもしれない。勧めてくれたのは親戚のだれかだったが、結果的に感謝の意は捧げてもいい。
もともと、成績は上のほうだった。ガリ勉をしなくてもそれなりに授業は理解できる。しかも本番にやたらめったら強い。中等部も試験勉強などろくすっぽぜず、運と気合いと家柄でサクラサクをつかんでみせた。
父も母も学歴を重視しない人だから、進学の話にはひどく疎いのだ。息子が入学した私立牡鈴学園がどんなとんでもない学校かということを、いまだにきちんと理解してすらもいないだろう。
よいところも悪いところも似たもの同士の両親を、遙兵は心から好いている。だからこそ、そこから距離を置く必要があった。
ものごとの全体像は、離れたところから眺めることでようやく掴めるものなのである。
サッカーのゴールキーパーが司令塔であるのと同じだ。
なにはともあれ、これから三年間、石にかじりついても頑張らねばなるまい。入学したはいいが、授業についていけませんでしたでは親戚じゅうの笑い者にされる。
世間体はどうでもいいけれど、親戚にばかにされると思うと腹がたつ。
中途退学などという情けない結末は迎えてなるものか。
牡鈴学園の学力レベルは全国でもトップクラスである。とくに高等部は灘や開成をしのぐとも言われている。日本の将来を背負って立つ若者を輩出すべく高度なカリキュラムによって少年少女を育てあげる、少数精鋭の最難関校。遙兵がそこに在籍するのは奇蹟としか言いようがない。まずはそれをきちんと認識するところからだ。
あの父が金を積んだとも思えないが、とりあえず合格だけはした。
ラッキーにしろ、破滅への序曲にしろ。
意地でも卒業してやる。
とりあえず、ネガティブ思考は最大の敵だ。
三年後、大学に行く必要はない。高校の三年間をしっかりと終えて、きちんと進路を決めさえすれば大役は果たしたことになる。
牡鈴学園高等部の入学者は東大、京大をはじめとする難関大学への進学を希望する者がほとんどだ。だからといって、その道がすべてではあるまい。
泣く子もだまる私立牡鈴学園で就職希望というのも、めったになくてある意味引く手あまたかもしれない。
高等部の入学式もまだなのに卒業後のことを考えている自分がおかしくて、遙兵は大きく伸びをした。
リラックス、リラックス。
昨夜詰めこんだばかりのダンボールをもう開けるのは微妙に納得がいかなかったが、箱のまま置きっぱなしもルームメイトに迷惑がかかる。二年生からは個室が与えられるけれど、一年生は二人部屋だ。
中等部では四人部屋だったので、プライベートが守られない生活には慣れている。遙兵は同室の人間をどうのと気にするタイプではない。だれとでもそれなりにうまくやっていける自信はあるつもりだ。
ただ。
今回は、さすがにギクリとした。部屋のドアに貼られていた紙を見て、うそだろと頭を掻きむしった。
『202号室
猛地 遥兵
弓ノ間 鉄人』
ユミノマ・テッド。
その名前は知っている。
むしろ、知らないほうがどうにかしている。
弓ノ間鉄人は、中等部三年のとき海外から中途編入してきた生徒である。
編入は原則的になしの牡鈴学園で、特例として迎えたのだからよっぽどなのだろう。
鉄人は、おそらくテッドの当て字であると思われる。アメリカか、どこかその近くの生まれらしい。
見た目はまったくの日本人だが、時雨努の言うには、編入のあいさつをいきなり流暢な英語でぶちかましたとのこと。
そればかりではない。来た早々、全国共通模試で一位を叩き出した。校内一位ではない。全科目満点で全国一位である。
クラスが別だったために、遙兵は話す機会もなかったが、噂はつねに聞こえてきた。
中間試験満点。模擬試験満点。期末試験満点。
ただ者ではない、ということはよくわかった。
特待生であること、特殊な事情で両親とは暮らしていないことなども噂好きの女子から聞いた。
高等部に無条件スライドするだろうことは想像がついたが、まさか寮生だとは。
しかも、よりによってそんなやつと一年間、同じ部屋でいっしょに暮らさなければならないとは。
胃がしくしくと痛んだ。
あの完璧な成績を維持するために、猛烈な勉強をしているにちがいない。
そして勉強嫌いの遙兵を、ばかにするに決まっている。
特待生だから、成績が落ちればおしまいだ。親に授業料を払ってもらえる遙兵とは大違いなのだ。
成績がよくて性格が上等なのもいる。時雨努がその典型である。冗談もちゃんと通じるし、頭がよいことを鼻に掛けない。だがそういう生徒こそ少数派なのだ。満点しか許さない完璧主義の人間など、どこか歪んでいるにきまっている。
まだ顔もあわせていないのに、遙兵は弓ノ間鉄人が鬱陶しくてたまらなかった。願わくばはなから相手にしてくれなければいい。へたに近づいたら優劣が目に見えて、いたたまれない。
弓ノ間の荷物は小さなダンボールひとつだけで、机の前に置かれていた。本人はまだいない。
遙兵はほっとして、荷物をほどきにかかった。早い者勝ちでふたつある机の一方をとると、まずは重い参考書類を本棚に押し込んだ。
漫画本はだいぶ処分してきたが、大事なものが数十冊ある。二段ベッドの枕元にも収納力のありそうな棚を見つけたので、そこに並べることにした。
弓ノ間は漫画などに興味なかろう。だが、オレはオレ。気にしたら負けだ。
弓ノ間の荷物は到着が遅れているのだろうか。まさか箱一個ということはあるまい。本人と同様、どこかで道草を食っているのだろう。
ひととおり片づけ終わっても弓ノ間は姿をあらわさなかった。
時計を見ると午後の四時。今夜は新入生歓迎のミーティングが行なわれる予定だから、それまでには到着すると思うのだが、それにしても遅すぎないか。
布団一式は寮から借りられることになっているので、取りに行こうと遙兵は立ちあがった。
出ようとドアノブに手をのばしたとき、タイミングよく扉があいた。
弓ノ間のおでましだ。
「あ、どうも」
遙兵はぺこんと頭を下げて、相手を見た。
チビだ。遙兵の目の高さに頭のてっぺんがある。
弓ノ間鉄人は学生かばんとボストンバックを両手にぶら下げて、お辞儀をした。
「ムーチョ・グスト」
「……へっ?」
「あ……いや、はじめまして。よろしく」
にこりとも笑わず、弓ノ間は機械的に言った。すぐに視線をすっと外し、机の上にボストンバックを置く。
遙兵が言葉を選んでいると、彼はそれ以上の自己紹介など無用と言わんばかりにダンボール箱に手をかけた。
ガムテープをびっとはがす。
配布されたばかりの教科書とわずかな衣類、洗面道具が中から出てきた。
漫画本がないことは予測できたが、参考書のたぐいもはいっていない。
片づけはほんの十分ほどだった。遙兵がぽかんとしているまに弓ノ間はてきぱきとそれをやってのけた。
疑問がむくむくとわきおこり、遙兵はついにこらえきれなくなって口をひらいた。
「あの、荷物、もしかしてそんだけ?」
弓ノ間は表情も変えずにこちらを向いた。
「そうだけど……なに」
「あ、いや、その。えらくまた、少ないんだな」
「そう?」
「本とか、参考書とか、あとから来るのか」
「これでぜんぶだけど」
さらりとかわして、弓ノ間はまた視線を反らした。そのとたん、尻ポケットで携帯電話ががんがんと鳴った。
着メロは、
――モーニング娘。
「……もしもし」
抑揚をまったくつけずに弓ノ間は応対した。
「はい……うん、まあなんとか。ドーント、ウォーリー。ハブ・ノー・フェア」
英語だ。アメリカから来たと言ったが、あらためて現実味がわいた。あまりにも早口で、なにを言っているのかわからない。
盗み聞きをするつもりはないのだが、狭い部屋だからいやでもきこえてくる。
「ありがとうございます、先生」
最後に日本語でそう言って、弓ノ間は電話を切った。
二段ベッドの上段から、ひかえめな寝息がきこえてきた。
そのときすでに遙兵の頭は、奇妙なルームメイトのことでいっぱいだった。
当初の予想を根底から覆し、遙兵のなかで弓ノ間鉄人の評価は完璧主義者から変人にまで落ちぶれた。
新入生歓迎ミーティングの最中、弓ノ間はずっとテーブルのすみっこでつまらなそうに出された菓子ばかり食っていた。自己紹介も名前だけでおしまい。ゲームにも参加せず、指名されてもにこりとも笑わない。
さすがに気を悪くした上級生が若干いて、あちこちから舌打ちがきこえた。
第一印象を自分から悪くしてどうするつもりなのだろう。共同生活は仲間のつながりが大事なのに、弓ノ間はそれを優先しようとしない。単なるわがままか、それとも対人関係が根本から苦手なのか。
遙兵には気になることがあった。最初に会話したときすでに気づいていたのだが、もしかしたら弓ノ間が人と接しようとしたがらない理由はそこにあるのかもしれない。
弓ノ間は、日本語の発音がおかしい。
海外に住んでいたのだから当然かとは思う。だが、そのためにいやな思いをして、それから話をするのが億劫になったということはじゅうぶんに考えられる。
小学生でもあるまいし発音でいじめもなかろうが、言葉というものは根が深いのだ。現に遙兵も、東北なまりをからかわれたことがある。
他人とは少しだけちがう個性は、恥ずべきものではない。英語も日本語も使いこなせる弓ノ間を遙兵はうらやましいとさえ思う。なにも包み隠すことなどなかろうに。
部屋に戻ってベッドにもぐりこむ前に、弓ノ間は自分から「おやすみ」と言ってきた。
意外だった。こちらを無視するつもりだろうと思ったら、どうやらそういうわけでもないらしい。もしかしたら性格的にぶっきらぼうなだけで、あれが彼の日常なのかもしれない。
変人だけど、けしていやなやつではない。
明日はもう少し話をしてみよう、と思ったところで心地よい睡魔が襲ってきた。
入学式の日は親と外で食事をとる生徒が多いため、一年生の夕食は準備しないとのことだった。
遙兵の両親は毎度のことながら式には出席できなかったが、どうやら弓ノ間の保護者も来ていないようだ。
声をかけるべきかどうか少し悩んで、遙兵はおずおずと切り出した。
「なあ、コンビニに弁当買いにいかねえ?」
霧船文庫から借りてきたらしい本に視線を落としていた弓ノ間が、ゆっくり振り向いた。
「べんとう……?」
「夕飯、ないんだってよ。オレ、弁当食うからさ、よかったらいっしょに」
「べんとうか」
弓ノ間はどんぐりのような眼をきょろっと動かして、言った。
「ハンバーガー食いたいな」
「え、夕飯にバーガーかよ」
「マクドナルド、いっぺん行ってみたかったんだ」
「行ったことないの、オマエ」
「うん」
ぱたりと本が閉じられた。その表紙をちらりと見て、遙兵は眉を寄せた。
「ンなの読むなよ、気色悪い」
「退屈だったんで」
おどろおどろしいガイコツの絵が血を流している。題名は、日本の厳選心霊スポット100。
「こういう本、めずらしいじゃん」
「めずらしい? オマエのほうがよっぽどめずらしいぜ」
オカルト関係はどうもいけない。真夜中に思い出すと眠れなくなる。遙兵は小さいころからお化けがものすごく怖かった。興味本位でそういう世界に関わってはいけないと、祖母にもよく言われたものだ。
「マクドナルドにしよう」と弓ノ間はまた言って立ちあがった。もうすっかりそのつもりのようである。財布をカーゴパンツのポケットにつっこんで、手櫛でわしゃわしゃと髪を直しはじめた。
「いいけど、マック、学校の近くだからバスで行くんだぞ」
「門限までにもどりゃいいんだろ。アスタ・ラス・ディエシィオーチョ・イ・トレインタ(6時半までに)」
「それ、どこの言葉?」と遙兵は訊いた。
「え?」
「こないだも、英語っぽくないのしゃべってただろ」
「ああ……そっか。つい、でちゃうんだよな。クセで」
弓ノ間はばつが悪そうに頬を爪で引っ掻いた。
「スペイン語だよ。おれ、プエルトリコって国にずっといたから」
「プエルトリコ? アメリカじゃないんだ」
「プエルトは自由連合州で、いちおうアメリカの領土ってことになってる。英語もつうじるし」
「ふーん……スゲエな」
「すげえ? なにが、どう、スゲエ?」
「だって、英語もスペイン語も話せておまけに日本語もちゃんとわかるんだろ。ハンパじゃねえよ。頭、ほんっとにいいんだな、オマエ」
弓ノ間は複雑な表情をうかべて、反論した。
「何カ国語か話せたところで、それがスゴイに結びつくってのが、解せないな」
「なに、いってんだ。じゅうぶんすごい。誉めてんだぜ? いちおう」
「ああ、そう。そりゃどうもありがとう」
弓ノ間はぷいっとそっぽを向いた。遙兵のせりふが癇に障ったようだ。
「親、プエルトリコにいるのか」
遙兵はずけずけと訊いてみた。
「たぶんね」
「たぶん?」
「親の顔、知らないから。ついでに素性も」
「そっか。なんかそんなことを女子が噂してた。ほんとだったんだな」
「おれ、有名人?」
弓ノ間はまた振り向いて、にたりと笑った。
はじめて見る笑い顔だった。
遙兵もつられて口元をゆるめた。
「そりゃ、あんだけ派手に登場すりゃな」
「フツーにしてたつもりなんだけど」
「あれでフツーだってぬかしやがったら、ぶん殴るぞ」
「どういうのを、フツーっていうんだ?」
「なあ、ボケてんのか? それともからかってやがんのか」
遙兵もかちんときて、語調に棘を含めた。天然のふりをしているならばひどくたちが悪い。ほかでもない私立牡鈴学園のSクラス特待生が、そんな簡単なこともわからないなんてあり得ない。
弓ノ間の顔から笑みが消えた。
声のトーンが落ちる。
「ごめん」
「えっ」
弓ノ間は視線をうろうろと彷徨わせながら、ぼそりと言った。
「おれ、人にどう接していいのかわかんなくて。気にさわったら、ごめんな。おれに、気ィ遣わなくていいからさ。おんなじ部屋で、迷惑かけっけど……無視して、いいから」
「なんだよ、それ」と遙兵はうなった。気にさわったのはいまのそのせりふのほうだ。話しあう努力もしないうちに関係を放棄しろだって。
「傲慢だな」
「ごめん」
「あやまったらそれで済むと思ってんだ。ンなとこも、なんだかな」
「じゃあなんていえばいいんだよ」
弓ノ間の唇がわずかにとんがった。
「そのくらい、自分の頭で考えろ。ったく、特待生のくせに」
「頼んでこうなったわけじゃない」
「あっそうですか。じゃあいいこと教えといてやるよ。S特狙ってる連中に気をつけな。階段とか窓際とか、うかつに近寄んないほうがいいかもな。おたくは無視すりゃそれでいいんだろうけど向こうさんはそのつもりねえだろうしよ。まっ、偏差値三十のおれにゃカンケーねーこったけど」
激怒するかと思ったのに、弓ノ間はふっと笑った。
「日本の学校も、あんまり変わりねーな。どこに逃げても、おんなじだ」
最後は消え入るようにつぶやいて、遙兵を見る。
そして信じられないひと言を吐いた。
「なんにも知らないくせに、おれに構うな」
「ンだと、この!」
遙兵はついにキレて、弓ノ間の胸ぐらをひっつかんだ。
そのまま壁に押しつける。
ダンッ、と大きな音がした。
弓ノ間の冷たい眼がまっすぐに遙兵をとらえた。
苛立ちでも、憎しみでも、蔑みでもない。そこにかいま見えた意志はほかでもない、拒絶であった。
遙兵のほうがぶるぶると震えながら、吊りあげる腕に力をこめた。
すました面をはりとばしてやりたい衝動に耐えながら、声をしぼりだす。
「なんなんだ、てめぇ。S特が何様だ。ヒラの生徒はひっこんでろってか? へっ、ご立派なこって。ああ、格差社会の上っかわなんてオレにはわかんねーよ。なんにも知らなくて悪かったな。心配しなくたって特待生サマにちょっかいはださねーよ。そんかわり……」
声が大きかったからか、廊下をだれかが走ってくる。
弓ノ間は唇の端をわずかにつりあげて、「殴れば?」と挑発した。
ドアが大きく開け放たれて寮長が飛び込んでくるのと入れ違いに、弓ノ間の身体は廊下まで吹っ飛んだ。
一階のいちばん奥、調理室のとなりにある薄暗い物置が反省室も兼ねていた。
照明はいちおうついているが、外からしか操作できない。窓もあるにはあるのだが、幅が狭いために脱走するには骨が折れそうだ。鍵をかけられてしまえば、反省がとどこおりなくすむまでおとなしく座っているしかない。
「おまえが悪いんだからな、ユミスケ」
ぜんぜん反省する素振りのない遙兵をぎろりとにらみ、弓ノ間は青く腫れあがった頬をわざとらしくさすった。
入寮してわずか三日目で、ふたりまとめて反省室送りである。霧船寮の歴史に残る迷場面にちがいない。
夕食はもちろん食べそこね、特待生のマクドナルド初体験も後日持ち越しとなってしまった。いざとなったらカップラーメンがあるが、弓ノ間と肩を並べてすするのもなんだかわびしい。
「ハリー・ポッターならスネイプにマイナス点つけられて降格ってとこか。くそ、窮地だぜ、ったく」
ぶつぶつと言った弓ノ間を遙兵はものめずらしそうに凝視した。
「ハリポタなんか読むの、おまえでも」
「なんでも読む」
「へー、意外」
「退屈だから」
「勉強、いつしてんだよ」
「学校でしてっだろ」
「そんだけかい」
「そんだけでじゅうぶんだ」
どこまで本気なのやら。遙兵にははかりかねた。だが不思議と、弓ノ間が冗談で言っているようには感じなかった。弓ノ間も一方的に殴られたわりにはなんだか楽しそうで、ちょっとだけ口数が多かった。
どうせ消灯まで解放されないだろう。三時間はやることもない。くだらないことをダベるのにはいい機会だ。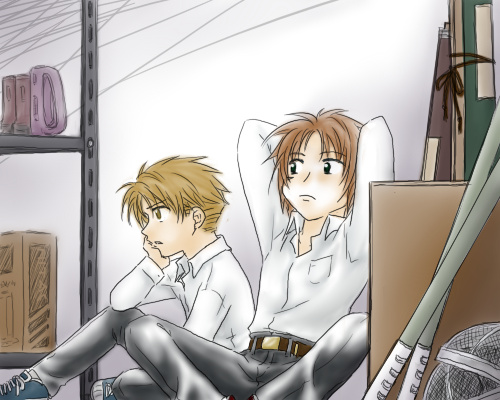
「テッドってあっちの名前?」
いちばん訊きたかったことを遙兵は切り出した。
「そう」
「まあ、だろうな。あの字だったらふつうテツヒトだろうしな」
「おたくのはーべいっちゅうのもけっこう変わった名前だと思うけど」
「死んだじいちゃんがよっぱらってつけた」
「ハーって呼んでいいか」
「いいぜ、テッド」
「あー、それ、ダメ」
「テッドはだめか」
「うーん、あんまその名前で呼ばれたくない……かな」
「わかった。けどユミノマ、ってのも、なんだかな。テツ、だったらどうだ」
「妥協してもいい」
「うし、じゃあ、テツな」
「ハー」
「うん?」
弓ノ間はなにか言いかけて、また口をつぐんだ。
そしてためらいながら、遙兵をちらりと見た。
「あのさ……」
「なんだよ」
「オレ、フツーじゃない……よな、やっぱ」
遙兵はあっけにとられて弓ノ間を見た。まだそんなことを気にしていたのか。
弓ノ間はひとりでつづけた。
「わかってんだ。おれ、フツーじゃない。フツーにしてろっていろんな人からいわれるんだけど、どういうのがフツーなのか、頭で考えてもぴんとこなくって……学校とかでどう振る舞っていいのかわかんないし、こないだだってゲームしてて、なにがおもしろいのかぜんぜんわかんなかった。ああいうの、楽しむモンなんだよな、フツーは」
「テツ」と遙兵は言った。「おまえ、そんなことずっと考えてたのか」
「ずっとじゃないけど、ときどき」
「日本にきたばっかりで混乱してっからじゃねえの」
「それもあるかもしれないけど」
「そういう他人の意見は、ウザいと思ったら、いっぺんスコーンと忘れてみろよ。頭であれこれ考えるからごちゃごちゃしちまうんだ。環境が変わったときってさ、あるぜ、そういうの。意味ねーのにへこんだりとかさ」
「そうかな」
「オレだって悩みあるぜ。なーに、慣れちまえばべつにどってことねえ。テツは頭いいんだから、すぐに慣れるって。ダメなのは、マイナス思考ってヤツだ」
弓ノ間はわりと素直にうなずいて、「グラシアス」と小さく言った。
奇妙な感じだった。
テストをただの一問もまちがえない弓ノ間鉄人が、己のことで迷っている。それを諭しているのが、あろうことか落ちこぼれ予備軍の自分だ。反対じゃないのか、普通。
普通じゃない。
フツーじゃない。
フツーじゃなくてなにが悪い?
なにも周囲にあわせる必要なんてない。自分で決めて、自分の道を往く。それがもっとも妥当なやりかただ。
距離を置いてはじめてその全体像がわかる。
弓ノ間とも、いっぺん殴ったら忌憚なく話ができるようになったではないか。
イメージに固執しないこと。人の言葉に縛られないこと。大事なのは、そこだ。
フツーじゃない弓ノ間とだって、いっしょに暮らしてみればいろいろと面白いこともあるかもしれない。
それに、課題で行き詰まったときにノート見せてもらえるかもしれないし。
いくぶん打算的ではあったが、遙兵はそう考えることにした。こう見えても根はポジティブなのだ。
そうと決まったら、このチャンスに多少なりとも恩を売っておくか……!
商売人の血がキラリンと輝いた、そのときだった。
「消灯でーす。電気けしまーす」
遠くで当番の声がした。
パチン。
電源の落ちる音がひびき、周囲は一気にまっくらになった。
遙兵はかちんと固まった。
暗闇で弓ノ間の声がする。
「完璧に忘れられちまったみたいだな、ここにいること」
至極のんびりと、まるで他人ごとのように。
ところが遙兵はそれどころではなかった。
必死に考えまいとしていた、とあるマイナス思考がむくむくと頭をもたげはじめる。
抑えようとしても、もう限界だ。
「てっ……テ、ツ」
「あん?」
「ち、ち、ちかくに、寄って、おねがい、こっちに、き、て、く、れ。たのむ」
「見えねーし」
「見えるんだってばよ!」
遙兵は叫んだ。
「先輩が見たってゆーんだよ! おおおおまえ、知らないのかよ。反省室には、で、出るんだぞ」
「なにが」
「すっとぼけんじゃねえよ! 幽霊だよ、ユーレイ!」
わずかな沈黙があった。
やがて暗闇から、とっても冷ややかな地獄の声がした。
「マジかよ」
九回裏、二死満塁から押し出しのフォアボールで逆転サヨナラのようなものである。
こうして特待生を尻に敷くチャンスは一瞬にして遙か彼方へと去っていったのであった。
「一年の猛地くん、ご自宅からお電話でーす」
寮内放送がキンキンとひびき、ブツリと切れた。
弓ノ間は読んでいた本から顔をあげた。
遙兵はベッドでいびきをかいている。放送にはたぶん気づいていない。
「ハー、でんわだってよ、デンワ」
揺り動かしてみたが、むにゃむにゃというだけで起きそうにない。
遙兵はいつもこうだ。天下泰平というかなんというか、いっぺん眠ったらテコでも起きない。
「しょーがねーの」
弓ノ間はスリッパを履くのももどかしく、一階の談話室に走った。公衆電話の受話器がはずされて、横に置かれている。
「あー、もしもし。代理ですが」
「遙兵?」
受話器のむこうから女性の声がした。
「すいません、遙兵、ちょっと寝ちゃってて。おれ、いっしょの部屋の者です」
女性はかなりの年配らしく、「あらあら、まんつまんつ」と少女のように笑った。
「電話があったこと、伝えときますんで……えと、どちらさま」
「ありがどな。遙兵のおばあちゃんだべ。おめさんは、それだば、ユミノマくんだべが?」
弓ノ間はびっくりして「そうです」と言った。
「ほーほーほー、んだべんだべ、テツくんだべ」
だべと言われても、返答に困る。日本語のスラングにまで精通してはいない。遙兵の田舎の方言だろうが、ちんぷんかんぷんでほとんど意味がわからない。
遙兵の祖母はひとしきりしゃべりまくったあと、「テツくん、遙兵となかよくしてやってけでな」と言った。
「ハー……遙兵くんには、お世話になっています」
「んだが。遙兵は悪たれだども、やさしいわらしこだべ。よろすぐな、テツくん、よろすぐな」
「……はい」
弓ノ間は受話器を置いた。胸がどきどきした。
遙兵が話したのだろう。勉強以外に取り柄のないつまらないルームメイトのことを、なんと伝えているのかは知らないが。
ただ、おばあちゃんの声は親近感を持っているふうだった。
それが無性に、嬉しかった。
「言葉が難関だな」
弓ノ間はひとりごとをつぶやいた。
今後の円滑なる人間関係のためにも、早急に秋田弁をマスターせねばなるまい。辞書さえあれば朝飯前なのだが。
遙兵がルームメイトでよかったと思った。なかよくとか、友だちとかという感覚はまだ持てないけれど、きっとうまくつきあっていける。無理を言って寮住まいに変えてもらった経緯があるから、銀町理事長にもよけいな心配をさせたくはない。
表面上であっても連れあいを持つことでカモ・フラージュにもなる。
遙兵の言ったとおり。頭であれこれ考えすぎないが勝ち。
この先、いくらでも危機はやってくる。だけどそればかり考えていたら埒があかない。
遙兵に言われてハッと気づいて、ようやく泥沼から抜け出せた。もちろんほんとうのことを、遙兵は知らないけれど。
告白するつもりもないけれど。
「キリタンポ、だっけっか」
くすっと笑って、弓ノ間は階段を駆けあがった。
おしまい
挿絵/斎里彩子さん
2007-03-30
